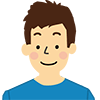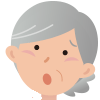認知症の人は、体験したことを忘れてしまいます。自分の体験の前後の繋がりがわからなくなってしまうのです。
たとえば、映画を途中から観たために、ストーリーがよく掴めない、という経験はあなたにもあると思います。
映画は他者のお話なのでいいですが、認知症の場合は自分自身の体験です。
体験の連続性がわかりづらくなり、自分自身、または自分の周りで起こっていることがわからず、自分と周囲の関係もうまく理解できません。
不安な気持ちになったり、混乱してパニックになったりするのです。
今回は、認知症患者さんの気持ちに立って、対応方法をご説明します。
目次 [開く]
認知症患者さん本人のペースに合わせよう
介護する側とされる側では、時間の流れが違います。
介護する側の価値観やペースを優先して、無理に急かしたり怒ったりしてはいけません。
あなたも慣れない仕事や新しい体験をするとき、内容を把握していないのに周囲から「早くやって!」なんて言われたらイライラしますよね。
「なんで早くできないの!?」
「どうしてもっと早く言わないの!?」
これは、時間の流れが違う世界に住んでいる認知症患者さんにとって、とても辛いことです。イライラして暴力をふるったり、暴言を吐いたりするようになるかもしれません。
結局は介護者側に跳ね返ってくるのです。
こどもが新しいことを経験するときに見守るように、どうぞゆったりした気持ちで見守ってあげてください。
根気よく繰り返しましょう
認知症の人の言動はわざとではありません。あなたをからかったり、意地悪をしようとしているわけでもないのです。
なんども同じことを聞いたり、ご飯を食べたことを忘れてしまったりします。
そんなとき、「さっきも言ったでしょ!」「何回言えばいいの!?」などは言わないでください。
認知症の人は、本当に忘れてしまっていて、それは注意力がないからではないのです。
脳の病気である、ということを忘れないようにしてください。
なんども同じことを聞かれたときは、できるだけ繰り返し話してあげましょう。
もしくは、半分聞き流す、という適当さも必要です。
聞こえなかったフリをするのもいいでしょう。
でもそのときは、「無視している」という態度ではなく、愛情を根底に持って笑顔で聞き流してください。
「ご飯を食べてない!」と言われたときは
時間が許すならば、余り物でいいので出してあげましょう。
本人は「食べてない」と信じていますが、実際には胃には食べものが入っていて満腹状態。実際には食べられません。
「もうお腹いっぱいで食べられない」と言ったら、「そうね、もうお腹いっぱいね」と言ってあげればいいのです。
「さっき食べたでしょ」と言って「そうだっけ?」というくらいの状態ならまだいいですが、本当に食べていないと信じきっている場合、意地悪をされていると思い込んだりします。
一度に伝えるのはひとつのことだけ
一度に色々な情報を詰め込んだ話し方は、認知症の人には理解できません。
ひとつのことを覚えるので精一杯なのです。
ダメな例
良い例
という風に、ひとつの行動ごとにひとつの情報しか入れないようにします。
認知症の人にとって、とてもわかりやすく、「理解できている」という自信にもなりますし、結局は介護者側も楽になるのです。
話すだけでなく、紙に書いてみる
認知症の人は、言葉で伝えるだけでは覚え続けていることが難しいです。
トイレやお風呂には、「トイレ」「お風呂」といった張り紙やシールを貼るとわかりやすいです。
洋服ダンスや食器棚にも「下着」「シャツ(半袖)」「お茶碗」「コップ」など、引き出しや棚ごとにシールを貼っておくとわかりやすいです。
電話には短縮ダイヤルに家族の電話番号を登録したら、「ここを押す」などの矢印つきの案内を貼っておくといいでしょう、
感情は確実に伝わっているということを忘れない
人間ですから、介護する側も疲れてしまったり、イライラしてしまうことも当然あります。
もし、認知症の人に冷たく当たってしまったら、深呼吸してひと呼吸置いてから、「ごめんね、あなたが悪いわけじゃないのよ」と優しく言ってあげてください。
認知症の人はボケてしまっているからなにもわからない、というのは嘘です。
認知症患者さんのいる介護施設では、意地悪…というか気が強い介護福祉士さんは嫌われ者だそうです(笑)。
優しい介護福祉士さんには、同じく優しく微笑んできたり、甘えてきたりするそうです。
怒られない、という安心感があるのでしょう。
でもそれは、認知症の人だけではないですよね。
具合が悪くて病院に行ったときに、「ああ、できればあの看護師さんじゃなくて、こっちの看護師さんに看てもらいたいなぁ」なんて思いはあるはずです。
意地悪な態度や、冷たい言葉、態度は確実に相手に伝わります。
周囲に誰もいないところで、認知症の人にしかわからないように毒を吐く人もいます。
これは立派な精神的虐待であり、相手の心はズタズタに引き裂かれてしまう、ということを肝に銘じましょう。
「あなたのことを気にかけていますよ」ということを言葉と態度で伝える
「安心していいのよ」「あなたのことはいつも気にかけているのよ」という気持ちは、どうすれば伝わるでしょうか。
日本人は、あ・うんの呼吸や相手の気持ちを読み取る気持ちが長けているとと同時に、言葉で表現するのが難しい国民性であると言われています。
言葉をかけるのが難しいときは、背中や腕をさすってあげたり、寄り添ってあげたり、一緒にお茶を飲んで会話をしたりして、「安心」「気にかけているという気持ち」が伝わるようにしてみたらどうでしょうか。
まとめ
いかがでしたか?
認知症の人と接するとき、ついついイライラしたり急かしてしまったりすることがあるかもしれません。
でも忘れてはいけないのは、認知症の人は脳にダメージを受けているということ。
冷たい態度、イライラ、怒りなど、負の感情は確実に認知症の人に伝わっています。
認知症初期では、「悪いわ…迷惑かけちゃうわ」と自信を無くしたり落ち込んだりします。でも周囲が厳しく当たると、だんだん防衛本能が働き、パニックになったり怒鳴ったり暴力をふるったり、という中核症状が出てきてしまいます。
優しい表情で話かけたり、「あなたのことを、いつも気にかけていますよ」という気持ちを持って接すると、きっと相手にも伝わって、関係がスムーズになります。
物忘れでなんども繰り返し同じ動作をしたり質問されても、始めて聞いたような素振りで付き合ってあげましょう。